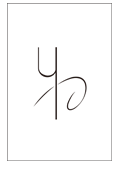chef's story VOL.2
「高度に洗練された食の中心。季節ごとの食材は変化に富み、古い伝統を新しい世代にきちんと伝えている。」
11月22日、アジア初となる「ミシュランガイド東京」を発行したミシュラン総責任者ジャン=リュック・ナレ氏は東京の食事情をこう評した。
『100年以上の歴史を誇り、公正かつ容赦のない評論で知られるミシュランの格付けが、
どう受け入れられるか、関係者でなくても興味をそそるところだが、
実際、今、東京の食は世界のどこよりも豊かになったのは事実だ。星の有無とは関係なしに、それこそ飲食店が何千店も存在する。
その中で輝きを放てるのは、ほんの一握りに過ぎないが、輝きを放つ店舗には共通する要素がありそうだ。
それが「エスプリ」である。』
料理に対するエスプリ、食材に対するエスプリ。
そんなエスプリを求め浅井シェフはカバン一つで、生まれ育った街「名古屋」から旅立った。
今から16年前のことだ。目指したのは東京・広尾にあるフランスレストラン。
伝統あるパリの名店の中にあって、開店4ヶ月でミシュランガイドの1つ星を獲得するという快挙を成し遂げたあの「レストランひらまつ」だ。
右手に履歴書、左手にはコックコート。一世一代の勝負である。
お客として「ひらまつ」に足を踏み入れると、そこは絢爛豪華(けんらんごうか)なヨーロッパの芸術的空間が広がっていた。
静粛なシャガールの絵画が容赦なく緊張を高めた。その極めて非日常的な空間で、
浅井シェフはどのタイミングで履歴書を出すべきかずっと考えていたが、なかなか話を切り出せず、結局、最後のエスプレッソを注文する時、ようやく話し出した。
やわらかな笑みをたたえた「ひらまつ」のマダムは、その時の浅井シェフに少なからず安堵感(あんどかん)を与えたという。
言葉少なに「す、すみません。実は…」とマダムに話しだすと、次の瞬間マダムはやんわりとこう告げた。
「今、平松はミーティング中ですので、すみませんが…」予想だにしなかったと言ったら嘘になる。
しかしこうもあっさりと断られると、気が抜けるのも当然だ。手に汗握る浅井シェフはひと呼吸し、
次の一手を模索しはじめた。食事も済み、ほどなく店を去らねばならない。このまま終わってしまうのか…。
後ろ髪を引かれる思いで、とりあえず席を後にした。
だが帰り際に一瞬、キッチンが垣間見えたことが、浅井シェフの中に次なる決心を芽生えさせることになった。
目にしたのは、これまで見たこともない巨大なキッチンだった。
そういえば、こんな話を聞いたことがある。フランス料理に適した厨房をフランスの料理人は日夜考えているという。
たとえば寿司屋の厨房をフランスでフランス人に作らせたら、きっとレベルの低いものしかできないだろうが、
日本で日本人に寿司屋の厨房を作らせたらうまいだろう。
それと同じようにフランス人の作ったフランス料理の厨房はよくできている。
そこにフランスと日本における料理の歴史、文化の違いがある…。浅井シェフは瞬間的にそれを感じたのかもしれない。
実際、彼らのふるう腕は機敏で繊細、そして大胆…。その光景は浅井シェフの目を一瞬にして釘つけにした。
三国シェフのビデオテープの残像とも重なる光景が、浅井シェフ情熱に再び火をつけたのだ。追い求めるものが確かにそこにはあったのだ。
店の外に出るとあたりは冬景色。2月の寒空の下、浅井シェフは店の前で長い間一人たたずんでいた。
コックコートを握る手はいつしか震えだしていたが、寒さのせいなのか、緊張のせいなのかは定かではなかった。
全身を突き刺すような寒さとは対照的に、浅井シェフの中では抱えきれない熱い想いが飽和(ほうわ)していった。
「どんなに笑われようが、今の自分をアピールするしかない。どうしても今日中に会いたい。」
浅井シェフはこう独りつぶやき、店が静まり返ると素早くコックコートに着替えた。
店の裏口へ急ぎ、深呼吸してから戸をたたく。それはまさに夢の扉を開いた瞬間でもあった。
ちなみに「ひらまつ」で浅井シェフを迎え入れたのは、困惑した表情の平松社長と、彼の右腕と言われた呆れ顔の河野氏だ。
そう、ミシュランで一つ星に輝いた「モナリザ」のオーナーシェフである。
河野氏は「フランスの三ツ星(レストラン)なら、今ごろ追い出されているよ」とため息まじりに言い放ち、
さらに追い打ちを掛けるように平松氏は「おまえ、血の小便がでるかも知れんぞ、それでもいいんだな?」とたたみかけた。
入社後、最初の数ヶ月はもちろん雑用ばかり。
しかし持ち前の勤勉さで周囲からの信頼を獲得し、鍋洗い・皿洗いから、半年後には前菜を任されるようになった。
文字通り“血の小便”は言うに及ばず、仕事に明け暮れた下積み生活が続いた。
「仕込みの量がまず半端じゃなかった。加えて、朝は築地に仕入れに出かけ、夜も遅くまで働きました。
そして3年目になる頃にはソース作りを任されるようになりました」と話す。
浅井シェフの表情は至って涼しげだが、たった3年で天下の「ひらまつ」でソース作りとは!
当時の「ひらまつ」のキッチンには30人ほどの料理人がいたはずだ。
彼らを差し置き、24歳の浅井シェフが大抜擢されていたということになる。尋常ではないことは想像に難くない。
その間、浅井シェフを支えていたものが、いつも頭の片隅にある三国シェフの存在だった。
“29歳で独立”した三国シェフを浅井シェフはいつしかひとつのバロメーターとして捉えるようになり、それに向けてひたすらまい進していたのだ。
そんな彼に次の切符を渡したのが「ひらまつ」の河野氏だった。
皮肉はあれど、なかなか他人を褒めることはない河野氏。そんな彼がある日、浅井シェフの肩に手をおきこう言ったのだ。
「おまえ、本当にがんばったな」
こうして浅井シェフは次なる武者修行の地・フランスへ渡ることになる。
本場フランスでも最高峰とされる「ジュエル・ロブション」が、浅井シェフを待ち構えていた。